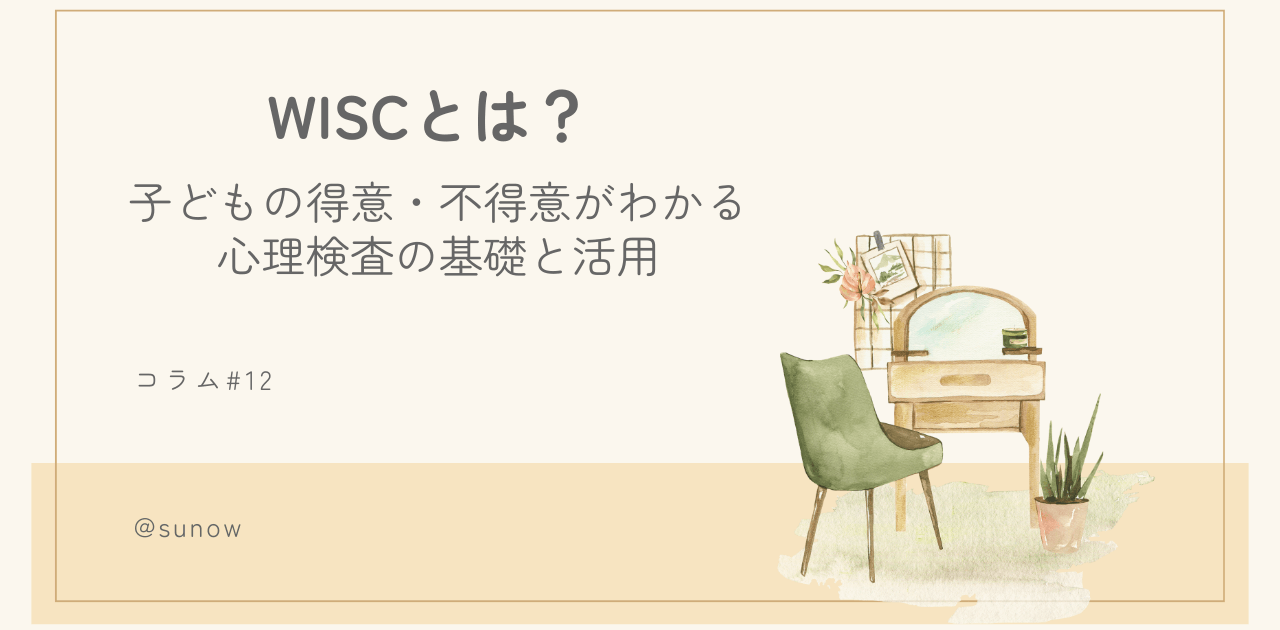「苦手な学習がある」「頑張っているのに結果に繋がらない」「どう伝えるのが本人にとっていいのかを知りたい」。
学校やその他の日常生活の場面で本人や保護者の方が悩んだり、不安を抱えたりすることは少なくありません。
そうした困り感の背景を理解し、支援の手がかりを得るために活用される代表的な心理検査が、ウェクスラー式知能検査、WISC(ウィスク:Wechsler Intelligence Scale for Children) です。
この記事では、
- WISCとは何か
- 検査でわかることと限界
- 結果の活用方法
をわかりやすく解説します。
学校現場や福祉現場、その他多くの場で耳にすることが多いWISC検査。
WISCについて理解を深めることは、今後の子どもとの関わりにおいて重要な意味をもつことでしょう。
WISCとは(WISC-Vの基礎知識・対象年齢・何がわかる?)

WISCは、子どもの知能や認知能力を評価するために開発された検査です。
広範囲にわたる検査項目によって本人の認知の特徴を評価することができ、得意なことや苦手のことを把握するのに役立ちます。
WISCは国際的にも広く認知されている検査であり、初版のWISCから、時代の変遷や教育的・心理的ニーズ、研究の進展に合わせて改訂を重ねてきています。
現在は2014年に導入された第5版であるWISC-Vが最新版です。
こちらのWISC-Vですが、日本語版が刊行されたのは2022年であるため、日本においては比較的新しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
前版であるWISC-Ⅳからの変更点もあり、新たに加えられた検査項目もいくつかあります。
この辺りはその後の解釈にも大きく影響するため、 WISC-Ⅳに精通している方であっても、WISC-Vについてはチェックしておくことが賢明かもしれません。
この記事でも、特徴的な変更点については一部触れています。
対象年齢とその他のウェクスラー式知能検査
WISC(WISC-V)の対象年齢は5歳〜16歳11ヶ月です。
WISCは児童用の知能検査であり、その他の検査としては幼児用のWPPSIと成人用のWAISがあります。以下にまとめます。
- WPPSI(ウィプシー):幼児用 2歳6ヶ月〜7歳3ヶ月
- WISC (ウィスク) :児童用 5歳〜16歳11ヶ月
- WAIS (ウェイス) :成人用 16歳〜90歳11ヶ月
いずれもウェクスラー式の知能検査であり、理論基盤が共通しているため、内容は違えど基本的な検査の枠組みは変わりません。
※上にあげた知能検査以外にもウェクスラー式の検査には、記憶検査もあります。
その他の「知能検査」と「発達検査」との違い
ここまで何度も出てきたように、WISCは知能検査であり、その名の通り本人の知能・認知能力を測定する検査です。
WISC以外の有名な知能検査として、田中ビネー、K-ABCなどがあります。
教育現場などでもよく耳するものかもしれません。
一方で発達検査とは、認知面や運動面、社会面など本人の発達の側面を幅広く評価し、年齢に対する発達の程度を測定する検査です。
発達検査には、養育者や子どもに関わる先生などがアンケートに回答するものと、子どもを直接観察して測定するものがあります。
代表的なものとしては、新版K式発達検査や遠城寺式乳幼児分析的発達検査法などがあります。
知能検査では認知能力に焦点を当ててIQ(知能指数)を算出するのに対して、発達検査では発達全般を幅広く測定し、DQ(発達指数)を算出します。
そのため勘違いされがちですが、WISCは知能検査であって、発達検査ではありません。
知能検査、発達検査どちらも広い意味で「心理検査」に含まれます。
WISC-Vでわかること(5つの主要指標)

WISC-Vは次の5つの指標で構成されます。
それぞれの指標が複数の下位検査から算出されます。
言語理解(VCI)
言語を使って理解・推論する力。語彙や概念の理解、言葉をもとに考える力に関わります。
視空間(VSI)
視覚的な情報を正確に把握し、空間的な構造を処理する力。図形や配置を理解・再構成する能力に関係します。
流動性推理(FRI)
与えられた情報から規則性や関係性を見出し、論理的に考える力。既存の知識に頼らず、新しい課題に柔軟に対応する力を反映します。
ワーキングメモリー(WMI)
情報を一時的に保持しながら操作・処理する力。複数の情報を同時に扱う課題や、学習時の注意制御に関わります。
処理速度(PSI)
視覚情報を効率的かつ正確に処理する力。日常の課題遂行のスピードや作業効率に影響する指標です。
全検査IQ(FSIQ)
上記の5つの主要指標から全体的な認知能力である全検査IQ(FSIQ)を算出します。
全検査IQの平均は100で算出されます。
WISC-Ⅳからの主な変更点
第4版(前版)であるWISC-Ⅳでは指標が以下の4つであり、これらから全体的な認知能力を解釈していました。
- 言語理解(VCI)
- 知覚推理(PRI)
- ワーキングメモリー(WMI)
- 処理速度(PSI)
WISC-Vにおける指標と見比べると分かるように、WISC-Ⅳにおける「知覚推理」が「視空間」と「流動性推理」の2つに分かれています。
「知覚推理」では、図形やパターンを見て理解したり、そこから論理的に考えたりする力が一括りに評価されていました。
一方、WISC-Ⅴではこれを分けることで、視覚的に正確に捉える力(視空間)と、規則性や関係性を見抜いて推論する力(流動性推理)をそれぞれ独立して測定できるようになっています。
この変更により、子どもの認知特性をより詳細に把握でき、強みと弱みを精緻にとらえて支援につなげやすくなりました。
また、ワーキングメモリーについてもWISC-Ⅳでは聴覚的なワーキングメモリーを中心に測定していましたが、WISC-Vでは視覚的なワーキングメモリーも対象となりました。
検査の流れと所要時間(お申し込み→聞き取り→実施→フィードバック)
検査を実施する上での流れや所要時間については各機関、受検者によっても異なりますので、ここでは基本的な流れとして、sunow(スノー)で実施する場合についてお示しします。
検査実施については、事前の聞き取りも含めておおよそ2時間〜2時間半程度です。
1. お申し込み
LINEまたは お問い合わせフォームからお問い合わせ。
心理士と日程調整を行い検査日の決定。
2. 検査実施
- 聞き取り(50分前後)
検査前のヒアリング。これまでの経緯や日頃の様子、困り感、検査を通して知りたいことなど幅広く面談で聞き取り。 - 検査実施(60~90分前後)
検査実施。必要に応じて休憩をはさむこともあり。保護者の方が別室で待機することも可。
3. 報告書作成
検査結果をもとに分析を行い、本人の得意な点や苦手な点を整理。
その上で、今後の対応や周囲の配慮について、わかりやすくまとめた報告書の作成。
4. 結果説明
結果説明。(後日)
日常生活で取り入れられる工夫や具体的な対処法についての提案。
結果の活かし方

WISCに限らずではありますが、心理検査は受けて終わりではありません。
その結果をどのように活かしていくかが重要です。
WISC を受けることで、本⼈の得意 ・不得意を把握し、困っていることの背景が理解しやすくなり、その結果、今後の⽀援の⽅向性や、 伸ばしていきたい部分などを考えるヒントになることが期待されます。
結果(5つの指標得点)を見て、よく凸凹があるという言葉を耳にします。
しかし、個人個人に得意なことと苦手なことがあるのは自然なことです。
大切なのは「凸凹がある」ということではなく、具体的に本人の得意なことは何なのか、そしてその得意をどう活かしていくことができるのかを考えることです。
sunowでは、こうした数値を通して本人を理解するためには、全検査IQや指標得点だけでなく、下位検査の得点や検査時の様子、事前の聞き取り内容も総合的に解釈し、報告書に盛り込んでいます。
報告書に書かれている数値だけでなく、今後の対応や周囲の配慮について書かれた所見も詳しく読むと良いでしょう。
また、結果説明を受ける際には具体的な対処法をはじめ、疑問に感じたことを質問することも重要です。
sunowに限らず、WISCなど心理検査を実施する機関は、結果の説明等を行う際には専門用語を避け、分かりやすく説明することが求められます。
WISCについての注意点

WISCを受けることで、本人の得意や不得意が把握できる、結果として普段の困り事の背景を理解しやすくなり、その後の支援にも役立てることができます。
また検査結果(報告書)があることによって、学校や支援機関に合理的配慮などを申請する際にも検討しやすくなると言えるでしょう。
このように、一見すると良いことが多そうに見えるWISCですが、注意すべき点もあります。
結果に振り回されすぎない
WISCの結果はあくまでも本人の一側面を見ているに過ぎず、全てを把握できるわけではありません。
もちろん結果を深く読み取ることで本人に対する理解を深め、今後の支援に繋げていくことは重要です。
しかし、だからといって検査の結果を絶対視するのは危険ですし、検査実施日のコンディションも結果に影響している可能性を考慮する必要もあります。
あくまでも参考情報であるということを忘れないようにしましょう。
再検査の目安
一度ではなく、しばらく時間が経ってから本人の様子を把握するために再検査を検討する方もいることでしょう。
また随分前の検査結果だと、現在はどうなのかが見えにくいために、学校やその他の支援機関からも再検査を勧めらることもあります。
しかし、一度受けた検査をもう一度受ける際には注意が必要です。一度経験しているため、練習効果が出てしまうこともあります。
そのため、基本的には再検査までの期間としては少なくとも1年以上、できれば2年の期間を空けると良いとされています。これらの期間を目安として再検査の時期を検討しましょう。
WISCの結果だけで発達障害がわかるわけではない
最後はとても多い誤解についてです。
WISCを受けることで、いわゆる発達障害(ASDやADHDなど)がわかると考えている方が多いようです。
これは、「WISCの数値に凸凹がある=発達障害」という意識が背景にあることが考えられます。
確かに、統計上は有意な関連が認められるかもしれませんが、WISCは発達障害を直接的に診断するためのツールではありません。
実際には行動面の特徴や、学校や家庭など幅広い場面での様子も含めて総合的に判断されます。
もちろん、他の心理検査を併せて実施する場合もあります。
そのため、WISCは診断の補助的なツールとして使用されることはありますが、あくまでも補助でありWISCだけで発達障害についてわかるわけではないことは理解しておきましょう。
受検先の選び方
WISCを受ける場としては、主に以下のように分類できます。
- 医療機関(児童精神科や小児科など)
- 公的機関(教育支援センターや発達相談支援センターなど)
- 民間施設(民間の支援施設やカウンセリングルームなど)
医療機関であれば保険が適用される場合や公的機関であれば、無料で受けられることもあります。
費用面は非常に大切な視点ですが、どこで受検するかについてはいくつかの視点から判断する必要があります。
多くの場合には検査をしてから後日、結果の説明を受けにいくという流れが多いと思います。
最低でも2回はその場所に行く必要があるため、当然行きやすい場所にあるということが大切な視点でしょう。
また、担当する検査者の資格や経験なども確認しておくと安心です。
さらに抜けがちな視点として、内容があげられます。
ここまでも述べてきた通り、検査は受けて終わりではなく、その結果をどう解釈し、どう今後に活かしていくかというのが最も重要です。
検査を受けて、結果の数値だけ渡されてもその後の支援への活用は難しいかもしれません。
実施後の報告書がどのような内容なのか、検査後のフィードバックはどのように行われているのかも確認しておくべきでしょう。
まとめ

WISCは、子どもの認知的な特徴を理解し、支援の方向性を考えるための検査です。
検査を受けることで、困りごとの背景や支援の方向性を考えるヒントになります。
大事なのは数値ではなく、そこから見えてくる「強み」と「課題」をどう活かすかということ。
学校や家庭での関わり方を調整することで、お子さんが自分らしく成長できる道が広がります。
もし「うちの子も受けた方がいいのかな?」「支援の方向性を一緒に考えたい」と感じられたら、どうぞお気軽にご相談ください。
sunow (スノー)でのWISCについての詳細はこちらからご覧ください。
WISCについて