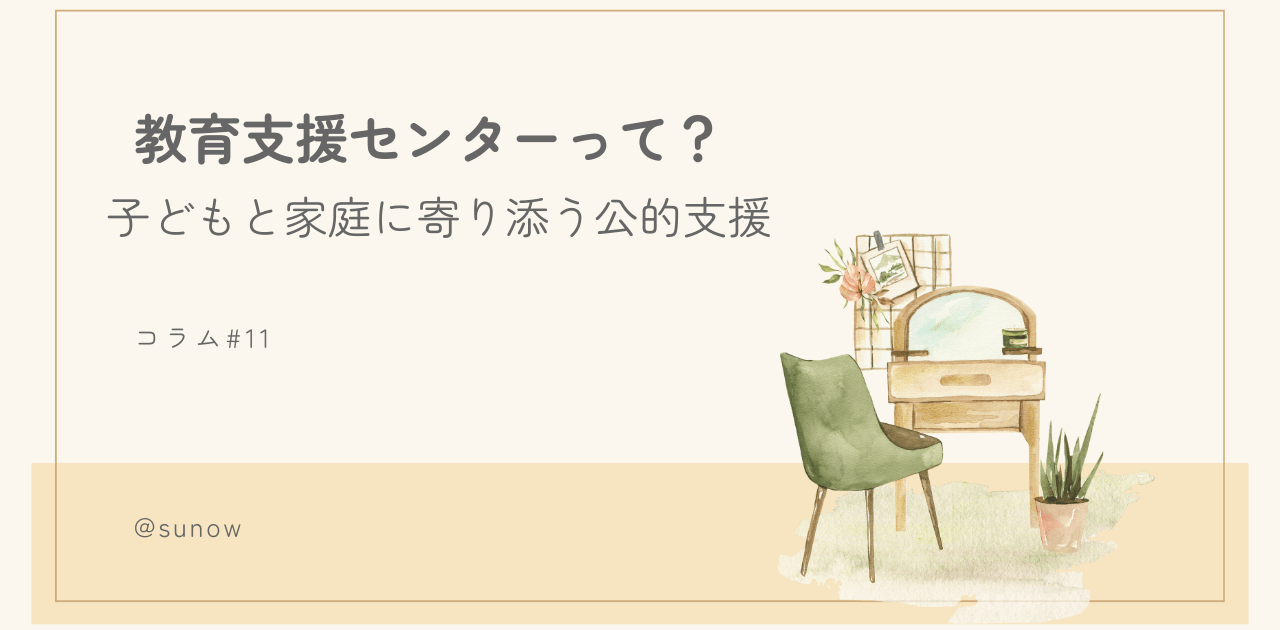最近よく聞く教育支援センターという言葉。不登校についての文脈で聞くことの多い言葉だと思います。
登校に悩んでいる時の一つの選択肢としての「教育支援センター」。
この記事では、教育支援センターの役割や利用方法、フリースクールとの違いについて解説します。

教育支援センターとは?(以前は「適応指導教室」と呼ばれていた)
教育支援センターとは、不登校の子どもやその家族を支援するために自治体が設置している公的な機関のことです。
端的にいえば、学校の代わりに学習や集団活動を行うことを通して、学校への復帰や社会的自立のためのサポートを受けることができる場所です。
この教育支援センターですが、かつては「適応指導教室」と呼ばれていました。もともとは、1990年に不登校支援の一環として導入されたのが適応指導教室でした。
その後、2003年に正式に「教育支援センター」と名称が変更されました。この背景には、不登校児童生徒の増加や、社会的自立を目指したより包括的な支援を重視しているという意味合いがあります。
こうした教育支援センターですが、自治体ごとに異なる呼ばれ方がなされているのも特徴です。
例えば、東京都目黒区であれば「めぐろエミール」、世田谷区は「ほっとスクール」、大田区は「つばさ教室」などです。
教育支援センター(旧称:適応指導教室)の目的は?
この教育支援センター、特に適応指導教室と聞くと、学校への復帰を目的とし、学校に戻ることを前提とした支援を提供しているイメージが強い方も多いのではないでしょうか。
確かに当初はそういった意味合いが強かったことも事実であり、現在でも学校復帰を重要視している教育支援センターも多くあることでしょう。
しかし、徐々に「学校に戻ること」だけを目的にせず、子どもが安心して過ごせる居場所づくりや、心のケア、学習支援を重視している自治体も増えてきています。
筆者もいくつかの教育支援センターを見に行ったことがありますが、自治体によって雰囲気や重視している考え方も様々な印象を受けています。
特に最近では、民間のフリースクールが自治体から委託を受けて運営している教育支援センターも存在します。いわゆる公設民営という形です。
誰が利用できる?対象・条件・費用の目安
教育支援センターは、主に不登校の小中学生 が対象です。地域によっては高校生の利用を受け入れている場合もあります。
実際、対象や入級の条件は自治体によって定められているので、お住まいの地域のホームページなどであらかじめ確認することをお勧めします。
例えば、目黒区であれば対象の欄に、「区立小・中学校に在籍する長期欠席等の状態にある児童・生徒で、本人及び保護者が入級を希望し、在籍学校の校長が必要と認めるものです。」と記載されています。
(参照:目黒区「学習支援教室『めぐろエミール』」)
費用についてですが、教育支援支援センターは公的な機関のため、基本的に利用料金はかかりません。
ここは大きなメリットと言えるでしょう。
教育支援センターで受けられる支援内容
教育支援センターでは本人や家庭の状況に応じたさまざまな支援が用意されています。
- 学習支援:在籍校の課題サポート、基礎学習、個別指導など
- 心理的支援:生活の相談、進路相談など
- 生活リズムのサポート:登校習慣づくり、生活習慣の改善など
- 交流活動:グループでの話し合い活動やレクリエーションなど
- 保護者支援:保護者相談や情報交換会、家庭での関わり方の助言など
このように「学び」と「心」の両面から子どもと家庭を支えるのが教育支援センターの特徴です。

利用までの流れ
教育支援センターを利用するまでの具体的な手続きは自治体によって異なりますが、ここでは代表的な流れを紹介します。(あくまでも一例です)
教育支援センターを利用したい場合は、まずは在籍校や教育委員会に相談するのが一般的です。
自治体によって不登校の相談窓口が異なる名称で設置されていることもあります。
まずはそうした情報を調べてみたり、在籍校の担任の先生やスクールカウンセラーなどに聞いてみたりするのがいいかもしれません。
- 在籍校(担任やスクールカウンセラーなど)や教育委員会(または不登校の相談窓口)へ相談
- 教育支援センターを見学・面談
- 利用申請
- 利用決定
- 通所前面談
- 通所開始
利用が決定したら通うスケジュールや支援内容、持ち物などを面談で相談して通所が開始されます。場合によっては、個別支援計画を作成して定期的に振り返る施設もあります。
教育支援センターに通うことで、学校の出席扱いになるの?
保護者にとっても本人にとっても「出席扱いになるのか」というのは大きな関心事でしょう。
教育支援センターへの通所は、在籍校や教育委員会との連携により出席扱いになる場合が多いようです。
具体的には、一定の要件を満たすことで学校以外の場での学習や活動が「出席扱い」として認められると定められており、この「学校以外の場」に教育支援センターやフリースクールなどが含まれます。
出席扱い等の要件については、文部科学省による「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」に示されています。
成績評価についても同様に通知が出されていますが、教育支援センターやフリースクール等の学校以外の場での学習や活動の「出席扱い」や「成績評価」については、こちらの記事をご覧ください。
(関連記事:フリースクール、学校の出席扱いになるの?)
教育支援センターとフリースクールの違い
教育支援センターと同様に、不登校に関連してよく聞く言葉がフリースクールだと思います。
最後に、教育支援センターとフリースクールの違いについて、簡単にまとめてみました。
| 項目 | 教育支援センター | フリースクール |
|---|---|---|
| 運営主体 | 自治体が設置する公的機関 | 民間団体・NPO・個人など |
| 費用 | 基本無料 | 利用料金は様々(入会金や月謝が発生する場合が多い) |
| 主な対象 | 不登校の小中学生(自治体によっては高校生も) | 施設によって様々(小学生~高校生・通信制生徒など) |
| 支援内容 | 学習支援・心理的支援・集団活動・復学支援など | 個別学習・体験活動・心理的支援など |
| 出席扱い | 一定の要件を満たせば出席扱い | 一定の要件を満たせば出席扱い |
最も大きな違いとしては、教育支援センターは自治体が運営する公的な機関で費用がかからず利用できる一方、フリースクールは民間が運営する学びの場であり、活動内容や雰囲気は多様ですが費用が発生するところでしょう。
(関連記事:フリースクールとは?学校に代わる新たな学びの場と可能性)
どちらも「子どもの居場所」として重要な役割を果たしていることは共通しており、本人の状況や各施設の特徴に応じて選ばれたり、場合によっては 両方を併用したりするケース もあります。
まとめ:自分に合う学びの場を見つけよう

教育支援センター(旧称:適応指導教室)は、不登校の子どもと家庭を支えるために自治体が設置する公的な支援機関で、費用の負担がない点が特長です。
一方、フリースクールは民間が運営する多様な学びの場で、活動の自由度や柔軟さが魅力です。家庭の状況や子どもの希望によっては、教育支援センターを利用しながらフリースクールを併用するといった選択も可能です。
まずは地域の相談窓口や学校、またはフリースクールなどに相談し、子どもに合った安心できる居場所と学びの形を一緒に探していきましょう。