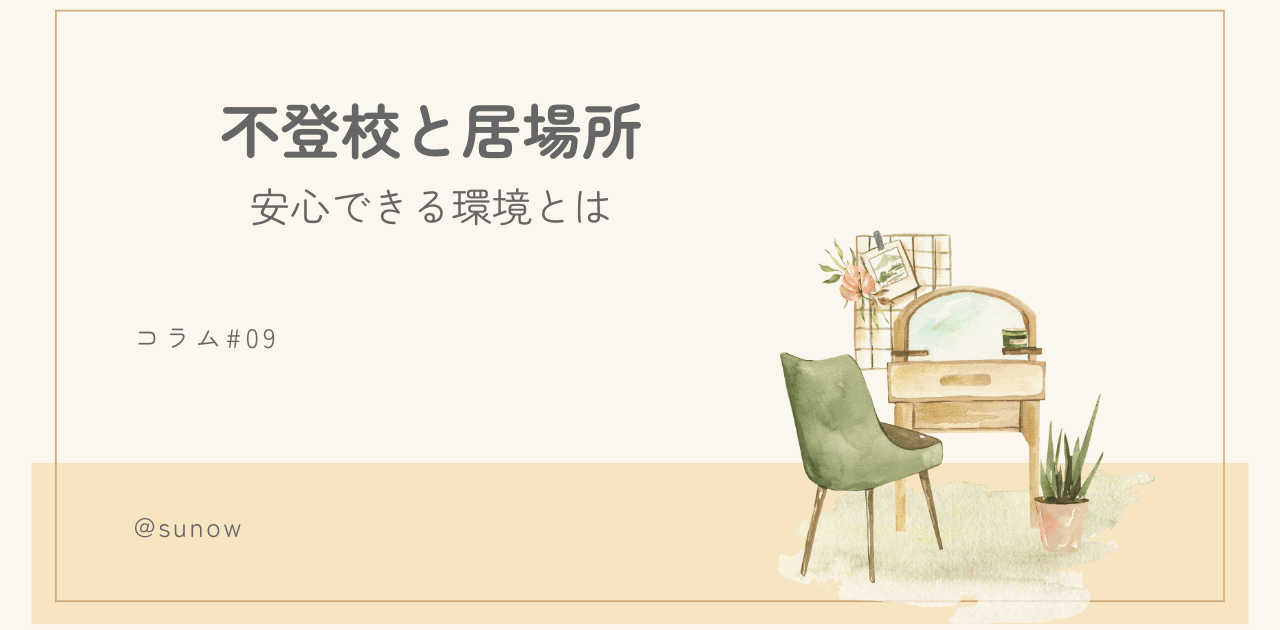「不登校」と「居場所」の関係
近年、小中高生の不登校の増加が社会的な関心を集めています。子どもが学校に行けない状態は、本人だけでなく保護者や家庭に大きな心理的負担をもたらします。
こうした状況で大切なのが、「居場所」と言われています。
居場所という言葉は聞き馴染みがある言葉ですが、この場合どういう場所のことを指すのでしょうか。
居場所とはすなわち、自分らしくいられる環境のことです。
これは物理的な場所のみを指しているのではなく、心理的な居場所のことも意味しています。
今日はそんな「居場所」について見ていきたいと思います。

不登校とは?
不登校は単に「学校に行かない」状態だけでなく、その背景に心理的・社会的な要因が絡む複雑な現象です。保護者や教育関係者など周囲の大人たちは本人の状況を理解することが、適切な支援の第一歩と言えます。
不登校の定義と現状
文部科学省によると、不登校とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
こうした不登校の背景には、心理的な要因や対人関係、環境的要因や学習に関する悩みなど、様々な要因があり、それらが複雑に絡み合っています。
一人一人状況は異なりますが、学校、もしくは教室を「居場所」と感じられていないことが共通していると言えるでしょう。
そういう意味で本人にとって安心できる居場所の提供が求められています。

居場所の考察ー誰にとっても必要な空間や時間
居場所は、本人が自分らしくいられる環境(空間・時間)のことです。心理的安全が確保された環境において、のびのびと学び過ごし、時折現れる困難をも乗り越えていくことができるものです。
こうした環境があることは、不登校かどうかに限らずに誰にとっても重要です。
もちろん学校がこうした環境になっていることも多くあります。学校、教室に自分の「居場所」を感じており、毎日を過ごしている人も多くいます。
そうした場合、例えば対人関係のトラブルや学習における悩みといった困難があっても、ご家庭や先生たちなど周囲の助けを借りながらうまく乗り越えていくことができるかもしれません。
しかし、学校や教室に自分の「居場所」を感じられていない場合はどうでしょう。
何となく苦しい場所、孤独を感じる場所、自分ではない感じがする場所・・・こうした環境において学ぶことは難しく、自信を失っていくことも容易に想像できます。
また、毎日学校に行ってはいても、「居場所」とは感じられず、教室の中で苦しんでいる児童生徒も増えている印象です。
モヤモヤしつつも教室で過ごす、周囲に嫌われないように無理して皆に合わせて過ごす。こうした日々が続いていけば、苦しさが増していき、限界が先に来てしまうかもしれません。
居場所は創り出すもの

それでは「居場所」はどうやって見つけていけるのでしょうか。
何度も述べている通り、自分らしくいられる環境が居場所のため、本人が自分らしく過ごせるかどうか、本人に合った環境であるかどうかという観点は非常に重要です。
一方で、そのようにぴったり合う環境が必ずしも皆にあるわけではありません。
自分にとっての「居場所」を得るというのは、「見つける」に留まらず、いわば「見出す」「創り出す」という視点も併せもち、「どうすれば自分らしくいられるのか」という問いに向き合う、ある意味で創造的な活動とも言えるのです。
すなわち、目の前の環境が自分に合うのか、自分を傷つけるものがないか、何となく安心して過ごせるかといった環境自体が安心を提供するという側面とともに、その場を自分の「居場所」にしようという本人の内的な努力が求められるという2つの側面があります。
おそらく前者が先に来るでしょう。しかし、ただ環境を与えられただけでなく、本人も一歩踏み出して、意識的か無意識的か自分なりに自分らしくいようと努力しているのです。
そういった経験が積み重なることで、その後関わる環境にも自分自身の「居場所」を見出していくこと(自分の居場所を創造する力)に繋がっていきます。
このことは周囲の大人にぜひ知ってもらいたいことです。
学校以外の居場所
学校以外の居場所として、教育支援センターや学びの多様化学校、フリースクールをはじめ、その他にも様々な支援に関わる団体が子どもの居場所づくりを行っており、多様な場が広がりを見せています。
しかし、既に述べたようにこの環境を与えられて終わりではありません。
与えられた上で本人は自分らしくいようと自然と努力をしていくことになります。
(関連記事:学びの多様化学校って?|増えていく学びの場)
本人にとっての居場所の大切さ
安心できる環境を与えられ、その後の本人の努力によってその環境が「居場所」になっていく。
そのため、その環境が本人にとって今どんな場であるのか、本人目線で捉えようとすることが周囲の大人には求められます。
例えば、実際に学校に来てはいるけれど、別室登校(保健室や相談室など)をしている例を見てみましょう。
教室では何となく苦しい思いをしていたけれど、別室登校によって徐々に元気を取り戻し、毎日のように別室に来るようになります。
これは本人にとって、自分に与えられた選択肢である「別室」を、自分の努力によって「居場所」としていくプロセスとも言えます。当然、「別室」において本人が安心できる環境を提供するよう努力した支援者も忘れてはいけません。
周囲の大人の視点では・・・
この状況を周囲の大人の視点で見てみるとどうでしょうか。
一見すると、「学校」に来てはいるのだから問題ない、もっと勉強をさせるべき、教室へ戻るよう働きかけようと考えてしまいがちです。
こう考えるのはある意味では当然の流れであり、一概に間違っているわけではありません。一人一人の状況によってそういった働きかけが求められることもあるでしょう。
本人の視点から見ると・・・
本人視点で捉え直してみると、少し違った見方ができます。
本人にとっては少しずつ自分らしく過ごせるようになってきた「別室」という「居場所」。そこに突如やってくる「勉強」や「教室復帰」への働きかけ。周囲の大人からのこのような働きかけは、本人から「居場所」を奪っている可能性すらあります。
本人のペースではなく、周囲の判断でその環境を取り上げてしまうことは、当然デメリットの方が大きいと考えられます。
この場合には「別室」での過ごし方の幅を広げていく、別の人や場と関わる機会を少しずつ作っていくなど、徐々に別の環境にも慣れていくようステップを踏んでいくことが現実的かもしれません。
その中で、本人も新たな環境で自分らしくいられる方法を考えていけることでしょう。
居場所で過ごすことを通して
居場所は学校復帰だけを目指すものではなく、子どもの成長や自律性を育むための重要な環境です。
新たに知り合った友達やスタッフと交流したり、普段はできない体験をしたり、自分のペースで学び過ごすことを通して、自己肯定感や自己受容を育むことができます。
(関連記事:「自己肯定感」と「自己受容」を育む ― フリースクールという選択肢)
実際に居場所を探す際には段階的に取り組んでいくと良いでしょう。
まずは情報収集をして、気になる場の見学や相談、体験などに申し込むことからはじめ、その後もまずは短時間の参加や無理のないスケジュールで利用することが大切です。
また、定期的に関わる支援者(スタッフ)と家庭が連携して情報を共有し、本人に合った支援やその後の働きかけなどを調整することも重要です。
まとめ:居場所が支える心と学び

不登校は単に「学校に行かない」ことではなく、心理的・社会的な要因が複雑に絡む現象です。その中で最も大切なことの一つとして、本人が安心して自分らしくいられる「居場所」をもつことがあります。
居場所とは物理的な空間だけを指すわけではなく、心理的に安全で、自分を受け入れられる環境も含まれます。学校や教室に居場所を感じられない場合、子どもは学びや交流で困難を感じ、自信を失うこともあります。
別室登校やフリースクール、学びの多様化学校など、多様な選択肢が現在は増えています。しかし、居場所は与えられるだけでなく、本人が自分の居場所として感じられるように努力していることも知っておく必要があります。
居場所を通じて、子どもは安心感を得て自己肯定感や自己受容を育み、少しずつ社会との関わりや学びに前向きになっていきます。周囲の大人は、子ども目線で環境の適合性を見守り、必要な支援を提供することが求められるでしょう。