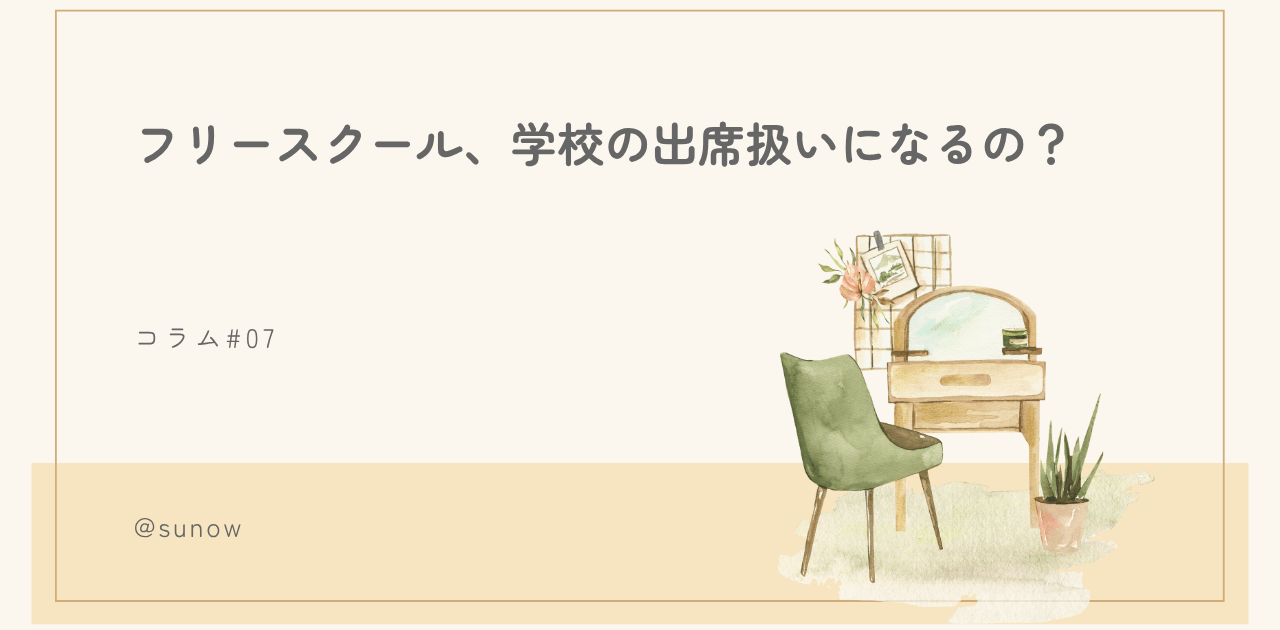フリースクールに通うことを検討されているご本人や保護者の方は多くの疑問を抱くと思います。その中でも多いのが、「フリースクールへ通うことが、学校の出席扱いになるのかどうか」。
今日はこんな皆さんが気になる疑問にお答えします。

文部科学省が認定する「出席扱い制度」
結論として、一定の要件を満たすことで学校以外の場での学習や活動が「出席扱い」として認められます。この「学校以外の場」に教育支援センターやフリースクールなどが含まれます。
この「出席扱い制度」は、不登校の児童生徒に広く学校以外での学びの機会を保障するために認められているものです。
文部科学省は「義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」で、出席扱い等の要件を示しています。
ざっくり言うと、以下のような項目です。
- 保護者と学校の連携
保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていることが必要。 - 公的機関と民間施設の選択肢
公的機関で指導を受けることが困難な場合、民間の施設も適切と判断される場合がある。民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては,校長が教育委員会と連携して判断することが必要。(この民間施設にフリースクールが含まれます) - 施設通所・入所の前提
施設に通所または入所して相談・指導を受けることが前提。 - 学習の評価と指導要録
学習内容が学校の教育課程に照らして適切であれば、学習の評価を適切に行い、指導要録に反映すること。
これらの要件に加え、フリースクールにおける相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指していること、さらに、児童生徒が自ら登校を希望した際に円滑な学校復帰ができるよう適切な支援を行っている場合、校長は指導要録上で出席扱いにすることができるという評価基準も設けられています。
上記の内容は、公的機関や民間施設に本人が通所または入所して相談・指導を受けている場合の出席扱い等の要件でした。
文部科学省はこれに加え、「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」についても示しています。
ここで示されている要件としては、以下の通りです。
- 保護者と学校の連携
保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていることが必要。 - ICTを活用した学習活動
ICT(コンピュータ、インターネット、遠隔教育システム等)や郵送、FAXなどを活用した学習活動であること。 - 訪問等による対面指導
対面指導が適切に行われることが前提で、学習支援や自立に向けた支援が定期的かつ継続的に提供されること。 - 計画的な学習プログラム
児童生徒の理解度を踏まえた計画的な学習プログラムが提供されること。 - 対面指導と学習活動の把握
定期的な報告や連絡会を通じて、校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること。 - 対面指導が適切に行われていること
ICTを活用した学習活動は、基本的に学校外で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であり、対面指導が適切に行われることが前提。 - 学習活動の成果評価
学習活動が学校の教育課程に照らして適切であると判断された場合、成果を評価に反映すること。
これらの要件に加えて、その学習活動が,本人が自ら登校を希望した際に,円滑な学校復帰が可能となるような学習活動であること、また本人の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に,指導要録上出席扱いとすることができるとしています。

「出席扱い制度」利用までの流れ
それでは、こうした「出席扱い制度」を利用する場合には、どのような流れで進んでいくのでしょうか。
ここではざっくりとしたイメージを持ってもらうために、民間施設に通所する際の簡単な例を紹介します。
- 「学校以外」の学習方法を決める。
学校以外の場に通所する場合には、実際にどこに通所するかを決めます。例えば興味のあるフリースクールに見学・相談に行って検討するなどです。 - 在籍する学校に相談する。
在籍校の先生に学校以外の場に通所を検討している旨を相談します。最初のステップとしては、担任の先生に相談することが多いかもしれません。フリースクールなどの民間施設に通所をしようとしている場合には、その施設のホームページなどを見せるとイメージが湧きやすいと思います。 - 学校内で検討
上記(2)を踏まえて、校長先生を含め学校内で本制度が利用可能か協議されることになります。この時点で、保護者の方に質問や確認などがあるかもしれません。場合によっては通所予定の施設と学校側の連携が必要になる場合もあります。 - 条件を学校と話し合う
その後、具体的に出席扱いとするための条件等について話し合うことになります。教材や学習内容はどのようなものか、学習状況の報告をどうするのかなど、詳細に話し合う必要があります。
上記(3)の学校内で検討している段階と同様に、(4)の実際に条件を話し合う段階においても、保護者と学校だけでなく、実際に通所することになるフリースクールなどの施設と学校の連携が必要になることも考えられます。特に学習状況の報告についてはきちんと決めておくことが望まれます。
学校との連携が可能かどうかなど、フリースクール側にもあらかじめ確認しておくと良いかもしれません。
ちなみにsunow(スノー)では、出席証明書等の必要書類についての作成も⾏いますし、学校で決まっているフォームがある場合には、そちらに合わせて作成することも可能です。学習状況や進捗などについても、必要に応じて学校との連携に最大限努めています。
成績評価ってどうなるの?
ここまでは、フリースクール等の学校以外の場における学習や活動が、在籍校における「出席扱い」になるのかどうかについて見てきました。
では、「成績評価」はどうなるのでしょうか。
結論として、2024年の8月に学校教育法施行規則が改正され、学校外での学習成果を学校の成績評価に反映することが可能になりました。
文部科学省は「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」において、その際の要件についても示しています。
以下に簡単にお示しします。
- 学習計画・内容の適切性の確認
学校は、不登校児童生徒の学習計画・内容が学校の教育課程に照らして適切であるかを確認する必要があること。 - 学校と保護者等の連携協力
学校は、保護者や教育支援センターやフリースクール等と連携し、定期的に不登校児童生徒の学習状況を把握することが求められること。 - 学校と児童生徒との継続的な関わり
学校は、訪問やICTを活用したオンライン指導を通じて、不登校児童生徒と直接関わり、学習活動の状況を定期的に把握し、関わりを維持していく必要があること。
文部科学省は、上記の通知において具体的な取り組み例も示しています。
- 1人1台端末を活用して、教育支援センターや自宅から学校の授業にオンラインで参加している不登校児童生徒の学習成果を成績に反映。
- 学校から届いたプリントや教材等を活用して教育支援センターや自宅で学習した成果を成績に反映。
- フリースクールに対して、定期的に不登校児童生徒の状況をまとめた報告書を学校に提出するように依頼し、学校とフリースクールが直接連絡を取れる体制を整備したうえで、フリースクールで学校の課題や定期テスト等の適切な教材に取り組んでいる不登校児童生徒について、その学習成果を成績に反映。
- 民間のeラーニング教材を活用して教育支援センターで学習を行っている不登校児童生徒について、教育支援センターの職員が保護者と連携しつつ、学習状況等を把握し、学校に情報共有することで、その学習成果を成績に反映。
特に成績評価の反映については、まだ始まったばかりの新しい制度であり、現場で十分に活用できているとは言い難いかもしれません。
いずれにしても、学校外での学習成果を学校の成績評価に反映させるためには、学校と保護者、また通所しているフリースクール等の施設間の十分な連携が不可欠です。
どのように連携していくことが可能なのか、このあたりを事前に十分に話し合うことが肝要でしょう。

まとめ
フリースクール等学校外での学習や活動が、学校の出席扱いになるのか、また学習成果を成績評価に反映できるのかについて見てきました。
「出席扱い」「成績評価」いずれにしても、学校、保護者、施設の十分な連携体制の構築が鍵と言えそうです。
どのように連携していくことが可能か、学校だけでなく、フリースクールにも見学・相談の際に十分に確認しておくことが重要です。
皆さんの歩む第一歩の、手助けとなりますように。