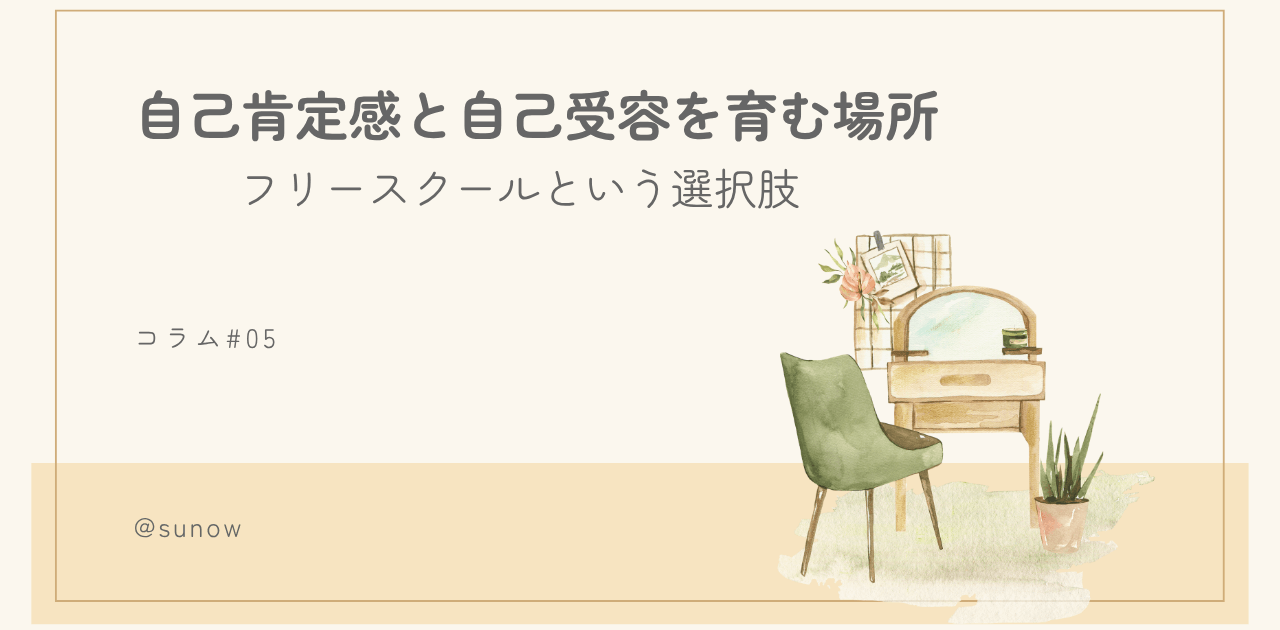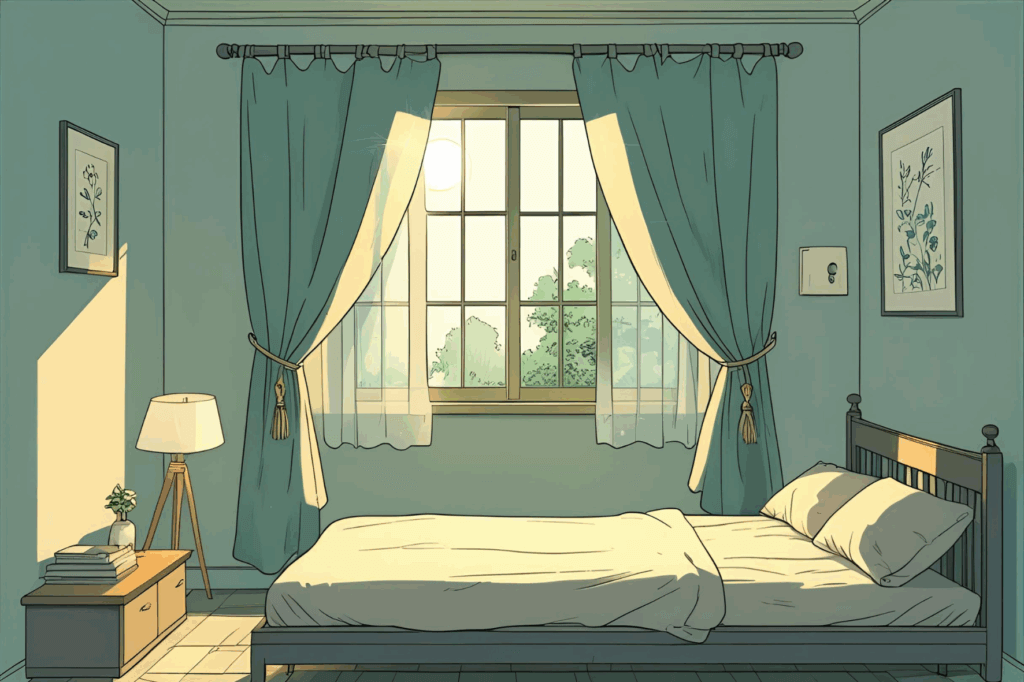
お子さんが学校に行かない。毎朝つらそうな表情で起きてくる姿を見て、何もできずに胸が締めつけられる──。
そんな保護者の方へ。
この記事では、「自己肯定感」や「自己受容」という視点から、いわゆる不登校の背景にある心の揺らぎを見つめ直し、「フリースクール」という選択肢がどのような役割を果たせるのかをわかりやすく解説します。
子どもたちが「ありのままの自分」でいられることの大切さと、それを支える居場所について、一緒に考えていきませんか?
「自己肯定感」「自己受容」とは?|意味と違いを解説
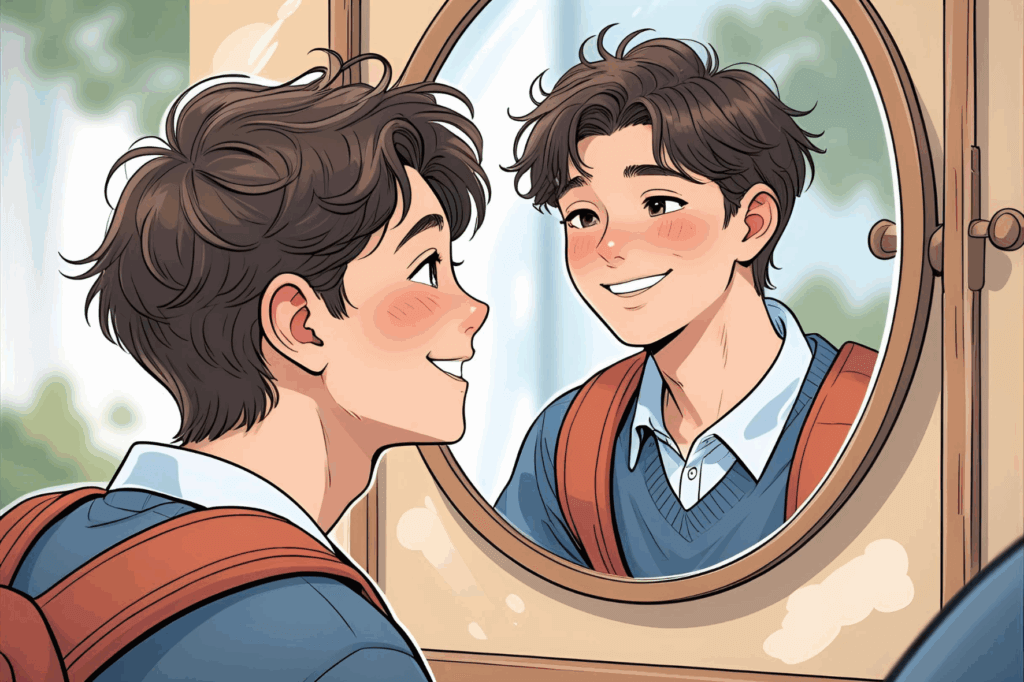
自己肯定感とは:肯定的に自己を捉えている感覚
自己肯定感とは、自己価値についての感覚であり、その名の通り肯定的に自己を捉えている感覚という意味で使われることが多いです。
きっと聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。「自己肯定感は高めるべきもの」というイメージを持たれている方も多いことと思います。
しかし一言に自己肯定感と言っても、その自己肯定感を支えるものにはさまざまなものが存在します。他者からの評価や学業成績、外見的な魅力など・・・どの部分に自己の価値を強く随伴させているかの程度は、人によって異なります。例えば、勉強はあまり得意でなくても気にしないが、人からどう思われているかだけにはとても敏感。逆に人からどう思われているかは気にしないけど、学業成績が悪いと自分の価値がないように感じてしまう。
どこに強く自己価値を依存させているかは人それぞれです。それまで過ごしてきた環境や周囲からの関わりによっても強く影響を受けていると言えるでしょう。
ということは、一言に「自己肯定感を高めよう!」と言ってもどのようにして高まっていくかは皆違うということです。「認める・褒めること」や「小さな成功体験の積み重ね」はもちろんとても大事ですが、効果は大きく異なります。
自己受容とは:「自分の良い面も悪い面も含めて、ありのままを認める」こと
自己受容は、自分の良い部分や悪い部分も含めて、それも自分の一部として認めることです。成績が思わしくなかったとしても、それはそれで受け入れることができます。こうした自己受容が土台となることで、自己肯定感は育まれるとも言われています。
すなわち、自己を受容できていないと、自己肯定感の低下を防ぐために、自分の肯定的な側面にばかり目を向けてしまい、否定的な側面から目を背けてしまうということが起こり得ます。こうした状況が続くと、できない自分は価値がないと思い込んでしまったり、強い理想の自己に囚われてしまい、自己不一致な状態になったりするかもしれません。
2つの違いと関係性|「いる」から「ある」へ
ある意味、以下のように整理できるかもしれません。
- 自己受容は「自分を認める基盤」
- 自己肯定感は「自分が自分であることへの確信」
自己受容が土台にあることで、自分を否定することなく、自分として存在することに安心できる感覚──すなわち自己肯定感が、自然と育まれていきます。
むしろこうした自己受容の土台がないと、既に述べたように学業成績や他者評価によって揺らぎやすい不安定な自己肯定感となってしまうかもしれません。もちろん、自己肯定感を語る上でこうした側面は見逃せません。自己肯定感は少なからず何かしらの要因に影響を受けるからです。
しかし、「自分はこう思っているんだ」「こう感じているんだ」という自己受容を繰り返していくことで、「自分はこれでいいんだ」「自分はこうなんだ」という安定した自己肯定感、換言すれば無条件の自己肯定感を育てていけることでしょう。まさに「どういるか」、から「どうあるか」への変化とも言えそうです。
不登校と自己肯定感・自己受容
自己肯定感や自己受容の土台が揺らいでいる状態では、「学校に行けない自分=だめな自分」と感じてしまうことがあります。それにより余計に自信を失い、視野が狭くなってしまうという悪循環も起こり得ます。
学校に行っていないというだけで「自分はだめなんじゃないか」と自己の価値が揺らいでしまうことも。こうした否定的な自己イメージは、自己肯定感の低下として表れることがあります。
自己肯定感が低下したときに見られやすい特徴
- 周囲と自分を比較しやすい
- 「期待に応えられない自分」を責めてしまう
- 「こんな自分ではだめだ」と思い込んでしまう
- 他者の目が過剰に気になる
- 意欲や行動力が低下する etc…
こうした状態の根底には「うまくいかない自分」「不安な自分」も含めて受け入れられないという、自己受容の難しさが隠れていることもあります。だからこそ、まずはどんな自分も否定せずに受け止められるような関わりや環境が求められるのです。
自己肯定感をどう育てる?|家庭でできるサポートと心がけ
自己肯定感を育むためには、その土台として自己受容が大切です。「できる自分」だけでなく、「うまくいかない自分」「不安な自分」も受け入れられる体験を重ねることで、「これでいいんだ」と思える安定した自己肯定感が育っていきます。
家庭では、本人が自分を否定するのではなく、少しずつ受け入れていけるような関わりがとても大切です。以下に、日常の中でできる実践例をご紹介します。
「存在そのもの」を認める言葉がけ
「がんばったね」「いてくれてうれしいよ」といった、“存在そのもの”を認める言葉がけが、安定した自己肯定感の土台になります。兄弟や友だちなど、他の人と比べず、「あなたはあなたのままでいい」と伝えることも重要でしょう。こうした関わりは、自己受容の感覚も育ててくれます。
成績や結果より「感情」や「努力」に注目する
結果ではなく、「悔しかったね」「よくがんばったね」と感情やプロセスに目を向けましょう。これは、自己受容を促し、安定した自己肯定感を育むことにつながります。
フリースクールとは?|自己肯定感が育つ理由
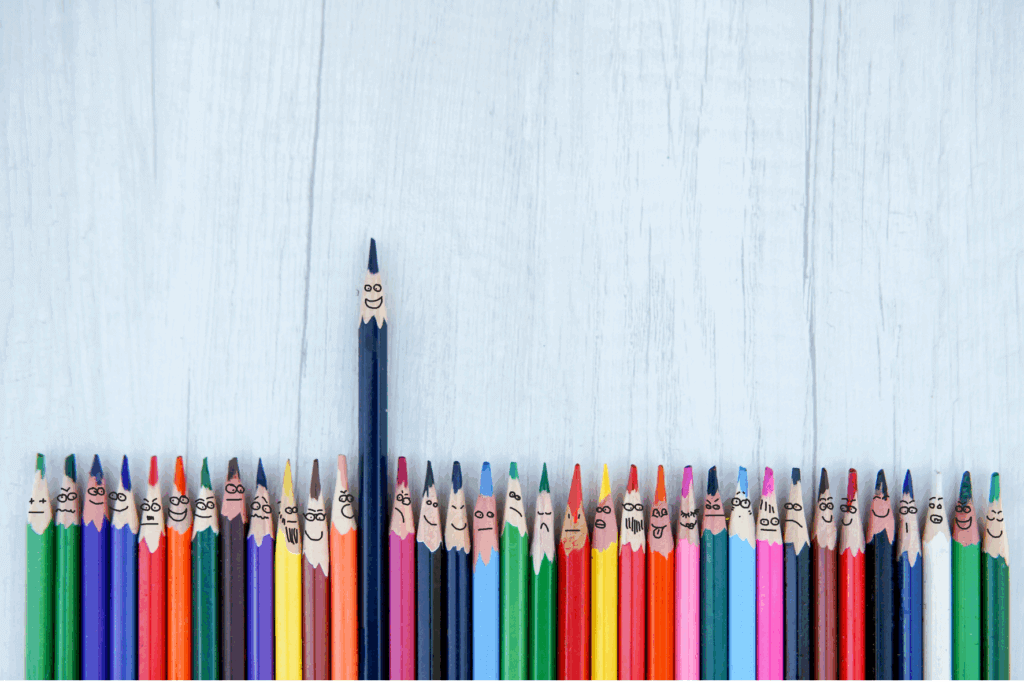
フリースクールの基本的な特徴(自由な学び・少人数・個別対応)
フリースクールは、学校の代わりに自分のペースで過ごせる居場所です。少人数制や個別対応により、子ども一人ひとりが尊重される環境が整っていることが多いです。
否定されない環境が「自己受容」を育む
否定されない関係性の中で、子どもは少しずつ「自分はこれでいいのかも」と感じ始めます。これが自己受容の第一歩と言えるでしょう。
自分で選び、自分で決める経験が「自己肯定感」を後押しする
「今日はこれをやってみたい」と自分で選ぶ経験が積み重なることで、「自分にはできることがある」という実感や「自分はこれでいいんだ」という感覚が育ちます。
もちろんこれ以外にもフリースクールのさまざまな要素が本人の自己肯定感や自己受容に影響していきます。総じて、「ありのままの自分」を受け入れて、「自分が自分であるという確信」を育むプロセスと言うことができるでしょう。
(関連記事:フリースクール×心理的ケア)
不登校支援に関わるすべての人へ|自己肯定感と自己受容のまなざしを
評価ではなく、「受け止める」まなざしを持つこと
何かをできた・できないで評価するのではなく、「そう感じているんだね」と受け止める姿勢や関わりが、信頼関係を築く土台になります。
自己肯定感は「周囲の関わり」で育つ
自己肯定感は、一人で育てるものではありません。周囲からの温かい関わりや言葉がけの積み重ねが、子ども自身の見方を変えていくものです。
学校だけがゴールではない、「ありのまま」でいられる場の必要性
「みんなと同じ」でなくてもいい、「今はここにいるだけで十分」そんなふうに思える場が、本人の再出発を支えます。
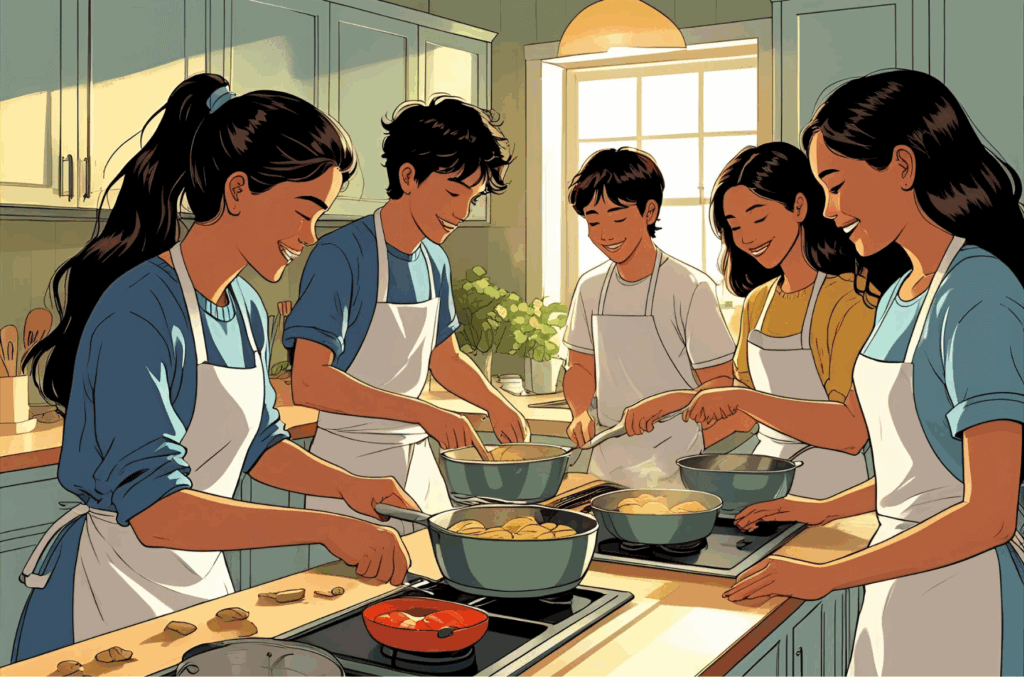
【まとめ】フリースクールで育つ“ありのままの自分”への信頼
自己肯定感や自己受容は、安心できる人や環境の中でこそ、ゆっくりと育っていくものです。
フリースクールは、安心して過ごせる居場所として、子どもたちが「自分って、これでいいんだ」と感じられる時間と空間を提供します。
「学校に行けない=ダメ」ではありません。むしろ学校に行かないというのは、本人の主体的な選択と捉えることができます。大切なのは、素の自分、今の自分を認め、小さな一歩を踏み出せる場があること。
お子さんのことで不安を感じている方へ。どうか一度、フリースクールという選択肢を検討してみてください。